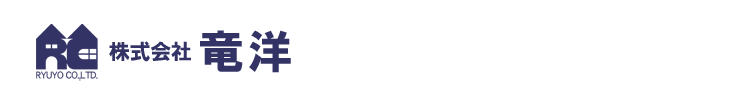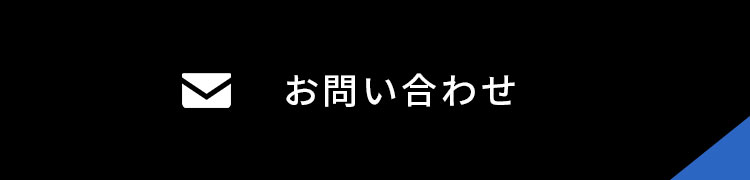100周年記念対談コンテンツ

100年の歴史の経緯について教えてください

社長:弊社は1926年(大正15)、私の祖父である鈴木寅一が東京・麻布桜田町にて創業したのが始まりです。その後、戦争の影響から、祖母の実家である磐田(当時の磐田郡竜洋町白羽)に移り、「鈴木板金」の屋号で板金業を開業しました。終戦の前の年である1944年(昭和19)のことです。私が入社したのは1972年(昭和47)頃。1981年(昭和56)に社長に就任し、そこから40年の月日をかけて、現在の「株式会社 竜洋」を作り上げていきました。
専務:父(代表取締役)が経営に携わる前は、どこにでもある地方の小さな板金工場だったように思います。家族経営で腕の良い職人さんが数名在籍しているような、こぢんまりとした工場ですね。それが父の代になってガラリと変わり、「組織として製造する」方針へと舵を切っていきました。新たな工場の設立や積極的な設備投資はその表れです。
社長:祖父も父も優れた板金加工職人でしたが、私にはそのセンスがなかった(笑)。会社を継続していくためには、別の角度からのアプローチが必要だと感じたんです。もちろん、紆余曲折の連続でしたけどね。「仕事もないのに工場なんて建てて大丈夫?」とか「試作品みたいな機械を導入するなんてリスクでしかない」とか。でも、そうやってつねに新しいことを取り入れる、時代見据えて先手を打つ、をしていかなければ、競合他社や大手には太刀打ちができない、業界で生き残っていけないと感じたんです。
専務:父(代表取締役)が経営に携わる前は、どこにでもある地方の小さな板金工場だったように思います。家族経営で腕の良い職人さんが数名在籍しているような、こぢんまりとした工場ですね。それが父の代になってガラリと変わり、「組織として製造する」方針へと舵を切っていきました。新たな工場の設立や積極的な設備投資はその表れです。
社長:祖父も父も優れた板金加工職人でしたが、私にはそのセンスがなかった(笑)。会社を継続していくためには、別の角度からのアプローチが必要だと感じたんです。もちろん、紆余曲折の連続でしたけどね。「仕事もないのに工場なんて建てて大丈夫?」とか「試作品みたいな機械を導入するなんてリスクでしかない」とか。でも、そうやってつねに新しいことを取り入れる、時代見据えて先手を打つ、をしていかなければ、競合他社や大手には太刀打ちができない、業界で生き残っていけないと感じたんです。
ここまで続けてこられた理由は
どこにあると思われますか?

専務:持ち上げるわけではありませんが、やはり父の功績が大きかったと思います。とにかく強気なんですよね。肝が据わってるというか。普通なら、仕事が急増して、現状では立ちいかなくなったことを理由に、新工場を建てたり、効率化を図るための設備を導入したりしますよね。でも、弊社は逆の発想。「まず環境を整える」ことで、他社との差別化を図ってきました。父曰く「これだけの人・設備・環境があるんだから、いずれ仕事も来るだろ」って(苦笑)。
社長:「仕事がない」というのは、単なる言い訳なんですよ。実際に、困っている人はいっぱいいますし、案件なんて無限に転がっている。なのに仕事が入らないのは、こちら側に問題があるからなんです。ならどうすれば良いか? こちらの環境を整えれば良いんですよ。他社が取り組まないような製造体制を作り上げる、ウチにしかない設備を導入する…みたいにね。実際に、弊社ではあらゆる設備メーカーの一号機や試作機がたくさんあります。まだ世に出回っていないものでも、可能性を感じたらできるだけ導入に踏み切ってきました。先ほども申し上げた通り、そのくらいの気持ちで先手を打ち続けないと「地方の板金屋」の枠から抜け出せないと思ったんです。
専務:いまだに全国から「工場見学をしたい」と問い合わせが来ますからね。そのくらい、業界における弊社の立ち位置というのは、異色のようなんです。ただ、私たちとしては特別なことをしている意識はないんですけどね。時代の流れやニーズを考えた結果であり、つねにチャレンジしていくという意識の結果として、必然的にこのような会社になっていきました。
社長:変に目立つようなことをしても、周囲からの反発が強くなるだけですから。基本的には「地道に、真っ直ぐに」という姿勢は崩さないように心掛けています。金属加工だけでなく、溶接や塗装までできるようにしたのだって、奇をてらったわけではなく、「その方がお客さんが喜ぶ」「竜洋を選ぶきっかけになる」と思ったからなんですよね。それ以上でもそれ以下でもありません。とは言え、全国的にもウチほど総合的に金属板金加工ができる工場はなかなかないと思いますけど(笑)。
社長:「仕事がない」というのは、単なる言い訳なんですよ。実際に、困っている人はいっぱいいますし、案件なんて無限に転がっている。なのに仕事が入らないのは、こちら側に問題があるからなんです。ならどうすれば良いか? こちらの環境を整えれば良いんですよ。他社が取り組まないような製造体制を作り上げる、ウチにしかない設備を導入する…みたいにね。実際に、弊社ではあらゆる設備メーカーの一号機や試作機がたくさんあります。まだ世に出回っていないものでも、可能性を感じたらできるだけ導入に踏み切ってきました。先ほども申し上げた通り、そのくらいの気持ちで先手を打ち続けないと「地方の板金屋」の枠から抜け出せないと思ったんです。
専務:いまだに全国から「工場見学をしたい」と問い合わせが来ますからね。そのくらい、業界における弊社の立ち位置というのは、異色のようなんです。ただ、私たちとしては特別なことをしている意識はないんですけどね。時代の流れやニーズを考えた結果であり、つねにチャレンジしていくという意識の結果として、必然的にこのような会社になっていきました。
社長:変に目立つようなことをしても、周囲からの反発が強くなるだけですから。基本的には「地道に、真っ直ぐに」という姿勢は崩さないように心掛けています。金属加工だけでなく、溶接や塗装までできるようにしたのだって、奇をてらったわけではなく、「その方がお客さんが喜ぶ」「竜洋を選ぶきっかけになる」と思ったからなんですよね。それ以上でもそれ以下でもありません。とは言え、全国的にもウチほど総合的に金属板金加工ができる工場はなかなかないと思いますけど(笑)。
人材育成、人材確保に関しても力を入れてきたそうですね
社長:結局、最後は「人」ですからね。どんなに組織や設備が揃っていても、そこに「仕事に向き合う姿勢」「仕事に対する思い」がないと、お客さんに満足していただけません。ですので弊社では、社会情勢や景気に関係なく、毎年のように若手の人材を採用し、OJT制度を軸にした人材育成に力を注いできました。また、待遇面や休日の取り方など、働く環境についてもつねに改善を重ねてきました。

専務:私が入社した15年前は総勢30人程度だったのが、今は130人いますからね。「人を採用し続けてきた」というのは、弊社が発展を続けてきた重要なポイントだと感じています。就職氷河期と呼ばれた時代においても、リーマンショックやコロナ禍の時にも、積極的に人材採用を続けてきましたから。そういったキツい時期に採用された社員が、今では会社の中枢を担うほどに成長し、支える力となっています。
社長:人材にしろ、設備投資にしろ、キツい時こそチャンスなんです。人材不足が深刻な現在では、雇いたくても応募がない。優秀な人材は大手にごっそり引き抜かれてしまいます。多くの会社が「人が足りない、育たない」と愚痴をこぼしていますが、弊社としてはそこまでの問題意識は抱いていません。むしろ30~40代の働き盛り世代がしっかりと経験を積んで活躍してくれていますので、しばらくはバランスの良い人材配置ができるように思います。
社長:人材にしろ、設備投資にしろ、キツい時こそチャンスなんです。人材不足が深刻な現在では、雇いたくても応募がない。優秀な人材は大手にごっそり引き抜かれてしまいます。多くの会社が「人が足りない、育たない」と愚痴をこぼしていますが、弊社としてはそこまでの問題意識は抱いていません。むしろ30~40代の働き盛り世代がしっかりと経験を積んで活躍してくれていますので、しばらくはバランスの良い人材配置ができるように思います。
ありがとうございます。
最後に“次の100年”に向けての展望を教えてください
社長:正直なところ、100周年ではなく「99周年」を祝いたかった(笑)。そうすれば「あと1年がんばれば100年だぞ」って士気が上がりますし、そうこうしているうちに、気づくと「101年目がスタートしたね」となる。前述した通り、私たちは、つねに時代の先を見据えて、攻めの姿勢で走り続けてきたという自負があります。だから、100年という区切りの良い年を意識し過ぎてしまうと、どこか足止めのきっかけになるような、一回リセットされるような気がしちゃうんですよね。
専務:「創業100年」というのはすばらしいことではありますが、あくまで「キリのいい数字」としか考えていません。私たちがやるべきことは今後も変わらないので、ひとつの通過点に過ぎないんです。まずは目の前のことに全力で取り組む。しっかりと「思い」を乗せて仕事をする。新しいことにチャレンジし続ける。そんな1日1日の連続が100年繰り返されただけであって、これが99年だろうと、200年だろうと、あまり関係ないんですよね。
専務:「創業100年」というのはすばらしいことではありますが、あくまで「キリのいい数字」としか考えていません。私たちがやるべきことは今後も変わらないので、ひとつの通過点に過ぎないんです。まずは目の前のことに全力で取り組む。しっかりと「思い」を乗せて仕事をする。新しいことにチャレンジし続ける。そんな1日1日の連続が100年繰り返されただけであって、これが99年だろうと、200年だろうと、あまり関係ないんですよね。

社長:私たち中小企業というのは、いつまで経っても日銭暮らしのようなもの。今は良くても、3年後にはあっさり倒産するなんてこともあり得ます。だからこそ、今、求められていることに社員一丸となって向き合い、「さすが竜洋」「竜洋に頼んで良かった」と評価していただけるような仕事をしていくことが大事になります。もちろんそのためには、私や専務をはじめとする上層部のリーダーシップも欠かせません。社員やそのご家族の人生も背負っているわけですから、会社を強くし、安心して働き続けていただけるような環境作りはつねに求めていかなくてはいけません。リスクヘッジなどにもつねに目を光らせながら、その瞬間における最善の決断を躊躇なくしていかなければならないと肝に銘じています。
専務:結局、シンプルなんですよね。今を大切に過ごし、それを地道に続けていく。その結果が、運とご縁のおかげで100年に届いたのですが、だからと言って、父が言うように、3年後も会社が存続しているか?なんて誰にもわかりません。私たちにできることは、これまでも、これからも「動き続ける」ことだけ。変に気負いしたり、驕り高ぶることなく、地道に、粛々と、頼ってくれるお客さんに応えていければ、それが一番の“次の100年”に向けての展望になると思います。
専務:結局、シンプルなんですよね。今を大切に過ごし、それを地道に続けていく。その結果が、運とご縁のおかげで100年に届いたのですが、だからと言って、父が言うように、3年後も会社が存続しているか?なんて誰にもわかりません。私たちにできることは、これまでも、これからも「動き続ける」ことだけ。変に気負いしたり、驕り高ぶることなく、地道に、粛々と、頼ってくれるお客さんに応えていければ、それが一番の“次の100年”に向けての展望になると思います。